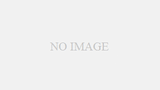「助産師に役に立つ資格って何があるんだろう」
「助産師としてもっとレベルアップしていきたい」
助産師として働いている、または助産師を目指している方で、こんな思いを持つ方がいます。
助産師はそれだけでも、十分に資格を活かしながら働ける職業です。
しかし、経験を積んできた助産師は、そこからさらにスキルを上げたい、視野を広げていきたいと考える方も多いです。
この記事では、助産師が持っていると役に立ち、スキルアップを目指していくことができる資格を、実際に助産師の資格を持っている私の目線で紹介します。
あなたの興味のある資格を探してみましょう。
また、助産師におすすめなようで実はおすすめしない資格についても解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
助産師おすすめ資格①アドバンス助産師
助産師おすすめの資格の一つ目は、アドバンス助産師です。
アドバンス助産師とは、助産師としての知識やスキルを客観的な評価により得られる資格です。
アドバンス助産師の資格を持っていることで、「自律して助産ケアを提供できる助産師」であるという証明になります。
そのため、転職などで他の医療機関で働く場合でも、自身のレベルを示すことができて、就職にも有利です。
アドバンス助産師の資格を取得するためには、まず臨床経験が5年以上必要になります。
5年以上の経験年数と、分娩介助件数100件以上など助産師業務経験を一定数以上こなしていることも必要な条件です。
そして、定められた研修や講義を受けることで、アドバンス助産師の資格試験への受験が可能となります。
試験は年に1回行われているため、1年以上前から研修参加などの準備をしていきます。
私自身も、アドバンス助産師の資格を持っておりますが、書類の準備など試験準備は意外と大変でした。
しかし、受験さえできれば試験合格は難しいものではありません。
アドバンス助産師は持っていて、損はないですし、試験のための研修や講義は助産師としての知識を深めることができるため、おすすめの資格と言えます。
今後も助産師として働いていこうと考えている人には、ぜひチャレンジしてほしい資格です。

アドバンス助産師の資格は5年ごとに更新が必要です。
常に、助産師としての最新知識をチェックする癖を付けましょう。
助産師おすすめ資格②産後ケアエキスパート助産師
産後ケアエキスパート助産師は、産前産後ケアのエキスパートとして認められた助産師のことを指します。
大阪府助産師会が主催する研修を受けることで、産後ケアエキスパート助産師の資格を得ることができます。
この資格は、もともと児童虐待防止の観点から、ハイリスク妊産婦への支援を目的に始まった認定制度です。
名前に「産後ケア」と入っていますが、対象となるのは産前から産後の母子です。
より良い産後ケアのためには、産前からのケアが重要であるためです。
産前産後にかけての、より専門的で高度な知識や技術を身に付けた助産師を目指す資格となっています。
産後ケアエキスパート助産師は、大阪府助産師会が開催する8日間の講習を受けることで認定を受けることができます。
前提として、産後ケアエキスパート助産師取得のための講習を受けるには、5年以上の実務経験が必須となることに注意が必要です。
助産師と言えば、「出産に関わり赤ちゃんをとりあげる仕事」というイメージは強いですが、働いていく中で、産前産後のケアに興味を持ったり、ケアの重要性を改めて感じたりする助産師もいます。
私は、産後ケアエキスパート助産師の資格は持っていませんが、医療機関で働く中で、社会的にハイリスクといわれる妊産褥婦さんに関わることも多いです。
ハイリスクとは、経済面の不安がある、周りに支援者がいない、自身に障がいがある、などさまざまな社会的リスクが挙げられます。
そのような方に対して、助産師としてどのように関わって行けばよいのかは、常に頭を悩ませています。
人によって背景も違うため、その人に合わせたケアが必要であることも、頭を悩ませる大きな要因です。
産後ケアエキスパート助産師を取得することで、ハイリスク妊産褥婦さんへのよりよい支援やケアを提案し、実践することが可能となります。
助産師としてのスキルアップを目指したい方や、出産だけでなくその前後の支援に力を入れたい方に特におすすめの資格です。

産前からの関わりが、産後の母児のより良い生活につながっていきます。
助産師おすすめ資格③乳房ケア
乳房ケアに関するおすすめの資格の一つに、BSケアプレゼンターがあります。
BSケアプレゼンターは、NPO法人BSケアが認定を行っている資格です。
BSケアとは乳房ケアを意味します。
母児にとってより良い母乳育児ができるようにケアをプレゼントし、さらにケアを行う仲間にその技術をプレゼンテーションするという目的の資格となっています。
BSケアプレゼンターの資格取得の条件は、助産師であることと法人の会員になっていることです。
その上で、定められた研修とトレーニングを受けることで、認定を得られます。
乳房ケアには「〇〇式」などさまざまな方法があり、資格がなくてもケアを行うことは可能です。
また、乳房ケアの基礎は、助産師資格取得の際に学んでいます。
しかし、ケアの認定を受けていることで、その技術を客観的に示すことができます。
BSケアの認定を持った助産師であるということで、ケアを受ける産後の方にとっては安心や信頼につながると言えます。
助産師の中には、お産よりも乳房ケアに興味を持つ人も多いです。
乳房ケアは奥が深く、いかに苦痛なくスムーズな母乳育児が続けられるかは、ケア方法が重要です。
BSケアプレゼンターは「スキルアップを目指したい」「乳房ケアに興味がある」という助産師にはおすすめの資格です。

産後の母乳育児で苦戦する人は多く、
助産師の適切なケアが苦痛の軽減につながります。
助産師おすすめ資格④妊産婦食アドバイザー
助産師におすすめの資格に、妊産婦食アドバイザーがあります。
妊産婦食アドバイザーは、母子栄養協会が認定を行っている資格です。
主に妊活中、産前産後の方への食事に関する指導やアドバイスが可能となります。
妊産婦食アドバイザーは、一般の方から管理栄養士や医療従事者までさまざまな立場の方が取得可能です。
一般の方には新たな知識を学ぶ場となり、ある程度の知識がある助産師などの職種にとっては改めて知識を学び、理解を深めることができます。
助産師や管理栄養士などの資格を持っている場合、栄養や食事についての知識はすでに学んでいます。
しかし、実際に食事内容のアドバイスや栄養指導を行うとなると、その対象者に合わせた特別な指導が必要となることもあり、指導内容に悩むことも多いです。
妊産婦食アドバイザーの資格を持っていることで、科学的な根拠をもとにした栄養学を身に付けることができます。
そして、その対象者に合わせた適切な指導やアドバイスを、自信をもって行うことができるようになります。
私は病棟で入院中の妊婦さんや産後の母児に関わることが多く、栄養指導を行う機会は少ないです。
しかし、外来の妊婦健診に来られる方と話す際に、食事や食べ物について聞かれることは多々あります。
食事や食べ物についての質問に対して返答に悩むこともあり、自信をもって答えられることばかりではないです。
妊娠に関連した栄養について改めて学べることは、助産師としての力を伸ばせることにつながるのはいうまでもなく、私も今後資格取得を考えたいと思う資格の一つです。

妊娠、出産前後の方は特に食事指導が重要であり、
その方に合った食事指導が求められます。
助産師おすすめ資格⑤専門看護師
助産師におすすめの資格に専門看護師があります。
専門看護師は分野別になっており、助産師におすすめの分野は、母性看護の専門看護師です。
母性看護の専門看護師は、産前産後の母子および家族への支援や、女性のライフサイクル全般にわたる健康への高度な援助ができる看護師です。
専門看護師は国家資格ではなく、看護協会が認定を行う資格ですが、専門看護師を持っていることは医療機関にとっても強みとなり、重宝される資格の一つです。
母性看護専門看護師の認定は、助産師だけでなく看護師でも取得することが可能です。
専門看護師を持っていることで、母子やその家族に対してより深く寄り添ったケアができるようになります。
その対象者にとって必要なケアや関わりを、高度な知識をもとに考えて、提供することができ、対象の母子ともより良い関係性が築けることにつながります。
不安を抱える母子やその家族にとっても、親身に関わり、適切なアドバイスやサポートをしてくれる看護師の存在は心強いものです。
専門看護師の資格取得は、臨床経験が5年以上あることと、大学院において必要な課程を終了していることが条件となり、その上で試験に合格すると認定を得ることができます。
認定された後も、5年ごとの更新が必要であり、常に知識や技術の更新や向上が求められます。
実際に専門看護師を取得する看護師は、働きながら大学院に通っている場合が多く、安易な気持ちで目指せる資格ではありません。
しかし、資格取得のハードルが高い分、持っている価値の高い資格であると言えます。

専門看護師は、院内でも重宝される資格の一つです。
助産師おすすめ資格⑥保健師
保健師は、助産師におすすめの資格です。
保健師は、看護師助産師と並んで、看護職と言われる3つの国家資格の1つです。
保健師は、医療機関だけでなく保健センターや地域の行政機関で働きます。
医療機関でなく、地域で働く保健師は特に、住民の健康を守る仕事があります。
住民の中には、産前産後の女性も含まれますし、その子どもも対象です。
特に、生活に不安があったり、自身の体調から出産・育児にサポートが必要であったりする方へのフォローが重要です。
助産師は病院で働いていることが多く、退院後の生活に向けた母子へのケアを行いますが、退院後については地域の行政のフォローがメインになります。
助産師が保健師の資格を持っていることで、退院後の地域の支援方法も把握したうえで入院中のケアができます。
また、不安が強い産後のお母さんに対して、地域でどのようなサービスがあるのか、などの情報提供もしやすくなります。
実際には、保健師の資格がなくても、助産師として十分に働けます。
しかし、保健師を持っていることで、入院中の母子への関わりがより質の高いものにできたり、退院後の母子のケアに興味を持つようになった際に、保健センターなどへの就職もしやすかったりします。
保健師の資格取得には、大学や大学院へ入学して勉強する必要があり、国家資格であるという点でも、比較的ハードルは高いです。
もともと助産師にも保健師にも興味があるのであれば、助産師や看護師資格取得のための教育機関を選ぶ際に、同時に保健師も取れる学校を選ぶことが近道と言えます。
自身がどんな助産師になりたいかを改めて考えたとき、妊産婦さんや育児をする方の生活に寄り添って関わっていきたいと思うのであれば、保健師は特におすすめできます。

地域での支援は、助産師よりも保健師の得意分野になります。
助産師おすすめ資格⑦NCPR
NCPRは、助産師に特におすすめの資格です。
NCPRとは、Neonatal Cardio-Pulmonary Resuscitationの略で、新生児の蘇生法を習得するための講座で、この講座を受けることでコース修了の認定を受けることができます。
出産の場に立ち会う際の助産師の仕事は、赤ちゃんを取り上げるだけではありません。
羊水の中から外の世界に生まれてきた赤ちゃんが、自分で呼吸が確立できるように助けてあげる必要があります。
呼吸確立を助けてあげる過程を、新生児蘇生法として学ぶのがNCPRです。
お産に立ち会う助産師にとっては、おすすめというよりも必須の資格という方がいいかもしれません。
私が通っていた助産学校では、NCPRの習得が必須項目であったため、学生時代にコースを修了することができました。
NCPRは、決まったアルゴリズムに沿って赤ちゃんの蘇生を行います。
NCPRを学んでおくことで、赤ちゃんがどんな状態で出てきたとしても、すべき処置が分かるため、落ち着いて対応ができるようになります。
生まれてすぐに自分でしっかり泣いて呼吸ができる赤ちゃんも多いですが、中には自分で泣くことができない赤ちゃんもいます。
生まれてすぐ泣くということは、呼吸ができているということです。
泣けない赤ちゃんをそのままにしておくと、低酸素状態となり、生命が危険な状態となります。
生まれてすぐの赤ちゃんに対して、迅速に適切な処置をすることが求められます。
お産に立ち会うスタッフとして、NCPRは必須の資格と言えます。

助産師として赤ちゃんを助けるために、NCPRは持っておくべき資格です。
助産師おすすめ資格⑧新生児集中ケア認定看護師
助産師におすすめの資格に、新生児集中ケア認定看護師があります。
認定看護師は、実践やケアの技術に特化して、その能力を認められた看護師のことを言います。
似ている資格に専門看護師がありますが、専門看護師は看護上の問題解決や研究が主になります。
認定看護師は専門看護師と同様に、看護協会が認定を行う資格で、医療機関が求める人材です。
認定看護師は、21分野に分かれており、その中でも新生児集中ケア分野が助産師におすすめです。
助産師が関わる対象には、新生児も含まれます。
新生児とは生まれて28日以内の時期の児を指します。
新生児へのケアやアセスメントは、成人とは異なった知識が必要です。
特に、生まれてすぐに自身で呼吸が確立できない児に対しては呼吸のサポートのため、人工呼吸器を付けることがあります。
また、新生児に適した治療環境を作ったり、ストレスの少ない状態にしてあげたりする看護ケアが求められます。
そのような、実際の看護の場で活かせる高度なスキルを身に付けているのが、新生児集中ケア認定看護師です。
実際に働く中でも、認定看護師はそうでない看護師の何倍もの知識を持っており、困ったときにはケア方法の相談を受けるなど、頼もしい存在です。
認定看護師の資格取得には、臨床経験5年以上と、認定看護師の教育機関で6か月の教育を受けて試験に合格する必要があります。
資格取得には、努力と時間を要しますが、言葉を発することのできない新生児により適切なケアが提供できる素敵な資格です。
助産師の中でも、新生児のケアに興味があるという方には、特におすすめです。

症状を訴えることのできない新生児へ、
最適な看護が提供できるのが新生児集中ケア認定看護師です。
助産師おすすめ資格⑨BLSプロバイダー
BLSプロバイダーとは、心停止や呼吸停止に対する救命処置の対応を学べる資格で、BLSとは「一次救命処置」を意味します。
一次救命処置は、心停止を発見した際にまず行う基本的な対応のことです。
BLSプロバイダーは、NPO法人日本ACLS協会が認定を行っている資格であり、助産師をはじめとした医療従事者だけでなく、一般の方でも受けることが可能です。
助産師として産科で働く中で、新生児の蘇生処置は多く当たりますが、小児から成人の呼吸停止や心停止にあたることは多くはありません。
しかし、全くないというわけではなく、妊産婦さんや産後の方の急変に当たる可能性はあります。
心停止時は、いかに早く心停止の判断をして、救命処置を始めるかが重要であり、その判断も含めてBLSで学ぶことができます。
助産師は特に、大人の急変対応に慣れていない人も多く、まずはBLSをしっかり身に付けておくべきです。
一般の方でも受講可能で、自動車免許の教習所などでも講習が行われており、BLSを学んだことがある人も多いでしょう。
BLSプロバイダーは、決められた研修やトレーニングを1日かけて受講し、試験に合格することで認定を得ることができます。
医療の現場に限らず、普段の生活の中でも遭遇する可能性のある急変対応を、自信をもって行えるように、BLSプロバイダーコースを受講することがおすすめです。

BLSは、医療従事者だけでなく一般人にも求められるスキルです。
助産師おすすめ資格⑩ACLSプロバイダー
ACLSプロバイダーとは、成人の心停止に対する二次救命処置のトレーニングシステムです。
一次救命処置であるBLSより医療的な処置で、心停止や呼吸停止状態の患者さんへの救命対応をしていきます。
BLSと同様に、助産師には直接的に必要な資格とは考えない方もいるでしょう。
しかし、助産師であっても病院内で成人患者さんを受け持つこともあります。
また、妊産婦さんが心停止や呼吸停止を起こす可能性もあります。
そのような状態は「急変」と言われるだけあって、予兆なく発生することが多いです。
その際に、医療従事者として、いかにスムーズに、必要な処置を行っていくかが、救命のために重要と言えます。
一般の方と異なり、医療関係者であれば、心停止や呼吸停止時にできる処置の幅が格段に広がります。
ACLSプロバイダーでは、医療従事者としての救命処置方法を学び、身に付けます。
救命と聞くと、難しくレベルの高いことのように思ってしまう人もいますが、その患者さんの状態によって行う処置は決まっており、根拠をもとに作られたアルゴリズムがあります。
ACLSプロバイダーコースを受講し、トレーニングを行うことで、実際の急変現場でも自信を持って動けるようになります。
助産師として、赤ちゃんだけでなく、お母さんを守るためにも、ACLSプロバイダーは身に付けておくべき技術です。

医療従事者の基本的な能力として、ACLSは学んでおくことがおすすめです。
助産師におすすめしない資格①産後ケアリスト
産後ケアリストとは、産後の女性を支援する専門家で、日本産後ケア協会が認定を行っている資格です。
産後ケアリストが助産師におすすめしない理由は、助産師がそもそも産後ケアの専門家であるためです。
産後ケアリストは誰でもチャレンジできる資格であり、医療従事者でない一般の人でも受験資格があります。
助産師になるために勉強をして助産師資格を持っている人にとっては、すでに勉強していることであり、「産後ケアリスト」と名乗るよりも、国家資格である「助産師」と名乗る方が、専門家としての信頼性は高いと言えます。
助産師が、あえて産後ケアリストをとる必要はないと考えています。
産後ケアリストの資格取得がおすすめな人は、保育士やベビーシッター、臨床心理士など産後の女性に関わる仕事についている人や、産後ケアに興味がある人です。
研修を受けて、試験に受かれば誰でも取得できる資格であるため、産後の女性に関わる職業についている方は、産後ケアリストでスキルアップを目指せます。
実際に助産師として働く中で、多職種と関わることが多いです。
特に、不安を抱えた産後の方には、退院後も踏まえたさまざまな方面からの支援が必要ですが、産後ケアに詳しい方ばかりではありません。
少しでも産後ケアに詳しい人が増えればその分、産後の悩める方へのフォローは手厚いものにできます。
産後ケアリストは助産師には必要ありませんが、世の中に求められる資格であると考えます。

「助産師を取るにはハードルが高いけど、産後のお母さんのケアを行いたい」
という方には、産後ケアリストはおすすめです。
助産師におすすめしない資格②栄養サポートチーム専門療法士
助産師におすすめしない資格に、栄養サポートチーム専門療法士があります。
栄養サポートチーム専門療法士は、低栄養状態の患者さんに対して食事内容や栄養バランスを考えたり、食事がとれない患者さんの点滴メニューや経腸栄養内容などの検討を行ったりします。
通常の栄養士でもこの業務はできますが、栄養サポートチーム専門療法士の資格を持っていることで、より深い知識をもとに患者さんに寄り添った業務ができるようになります。
栄養サポートチーム専門療法士は、助産師でも資格取得が可能です。
しかし、助産師にはおすすめしないという理由は、妊産婦食アドバイザーの資格の方が助産師のスキルアップには適しているためです。
妊産婦アドバイザーについては、助産師おすすめ資格④で紹介していますが、妊活中の方から産後まで助産師が関わる幅広い対象の方の栄養について学び、専門的な知識を身に付けることができます。
栄養サポートチーム専門療法士は、成人患者さんへの看護やケアを行っているスタッフに特におすすめと言えます。
栄養サポートチーム専門療法士は、栄養のスペシャリストであり、病院内でチームとして活躍する職業の一つです。
食事の進まない患者さんや、点滴で栄養を補わなければならない患者さんへの介入は、看護師や医師だけでは検討が難しい場合もあり、そんな時に相談に乗ってくれる専門家です。
看護師でも資格取得可能であり、「患者さんの栄養状態の維持・向上のためにもっと知識を増やして実践に生かしたい」という人におすすめの資格です。

助産師の方でも、今後成人看護に関わっていきたいと考えている場合は
取得する意義のある資格とも考えられます。
助産師におすすめしない資格③JALA
JALAとは、「無痛分娩関係学会」のことで、助産師に向けた資格制度はありません。
JALAでは、麻酔科医師を中心に無痛分娩を安全に受けられる、行えるようにするための情報提供や取り組みをしています。
JALAは、以前は無痛分娩に関わる医療従事者にむけた講座を頻繁に開いていましたが、現在は講座動画の配信のみで、2021年で更新は止まっています。
基本的な内容の学習にはよいかもしれませんが、最新情報にアップデートされていない可能性もあります。
しかし、公式ホームページ内には無痛分娩に関して、患者さん・スタッフそれぞれに向けた情報提供が適宜されており、無痛分娩に関わる医療従事者としては有益な情報が載せられています。
無痛分娩はさまざまなリスクが考えられ、助産師にとっては通常の分娩よりも知識や対応力が必要となります。
しかし、世間では無痛分娩の需要は増えている現状であり、直接お産に関わる助産師はニーズに合わせたケアを提供していかなければなりません。
JALAのホームページから、無痛分娩に関する最新の情報をチェックしてみましょう。

無痛分娩を希望する人は増えている印象があり、
助産師は最新情報をキャッチしながら安全に分娩を進めるスキルが必要です。
助産師におすすめしない資格④医療系資格試験教材の【アステッキ】
医療系資格試験教材のアステッキは、助産師にはおすすめしません。
医療系資格試験教材のアステッキは、知識のない一般人でも医療系の資格取得を目指せる学習ツールであるためです。
取得可能な資格は、下記です。
- 呼吸療法認定士
- 終末期ケア専門士
- 急性期ケア専門士
- 在宅看護指導士
- 家族ケア専門士
- 在宅介護指導士
- 終末期ケア上級専門士
- 透析技術認定士
- 糖尿病療養指導士
そもそも国家資格を持っている助産師には不要です。
助産師は看護師資格も持っているため、上記の内容に興味がある方は、専門看護師や認定看護師を目指す方が意義があると言えます。
医療者以外の一般の方で、上記の分野に興味があったり、関わる機会があったりする方には、医療系資格試験教材のアステッキでの学習はおすすめできます。
医療系資格試験教材のアステッキは、スマホを利用しサポートを受けながら資格取得を目指せます。
助産師としてのスキルアップを目指す人には特におすすめではなく、認定看護師などのような、もっと実践に生かしやすい資格取得を狙う方が有益であると考えます。

助産師がスキルアップを目指すなら、
他におすすめの資格がたくさんあります。
まとめ
この記事では、助産師におすすめの資格・おすすめしない資格を紹介しました。
| おすすめの資格 | アドバンス助産師 | 助産師のレベルを示せる |
| 産後ケアエキスパート助産師 | 産後のケアに特化した助産師になれる | |
| 乳房ケア | 母子に優しい乳房ケアを習得 | |
| 妊産婦食アドバイザー | 妊活中から産後までの食事指導に役立つ | |
| 専門看護師 | 母性看護に特化した助産師になれる | |
| 保健師 | 退院後の支援にも目を向けられる | |
| NCPR | 赤ちゃんを守るために必須の資格 | |
| 新生児集中ケア認定看護師 | ハイリスクな赤ちゃんのケアに特化した助産師になれる | |
| BLSプロバイダー | 心肺停止時の初期対応を身に付ける | |
| ACLSプロバイダー | 心肺停止時の医療者としての対応を身に付ける | |
| おすすめしない資格 | 産後ケアリスト | そもそも助産師は産後ケアの専門家 |
| 栄養サポートチーム専門療法士 | 周産期に限らない栄養管理の専門家を目指す | |
| JALA | 無痛分娩の情報提供の場となっている | |
| 医療系資格試験教材の【アステッキ】 | 一般の人でも医療関係の資格取得を目指せるツール |
助産師としてスキルアップしたい、自身の興味のある分野を深めたい方は、この記事を参考に、新たな資格取得を目指してみてください。
知識を深めていくことで、助産師の仕事がより一層楽しくなるでしょう。